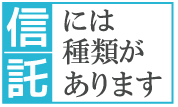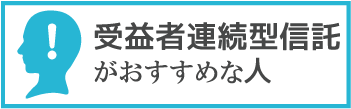家族信託は、自分の資産を信頼できる家族に託して将来の管理や運用を任せる制度です。その設計において「胎児を受益者にできるのか?」という疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。特に、相続や資産承継の場面でまだ生まれていない子どもを対象にしたい場合、この点は重要な論点になります。法的な可否や対応策について、本コラムで解説していきます。
結論から言えば、胎児を家族信託の受益者に指定することは、原則としてできません。家族信託では、受益者が信託財産から利益を受け取る権利を持つ主体となりますが、法的には「権利能力があること」が前提となります。胎児は法的に人として扱われる場面が限られており、相続などの一部の例外を除いて、原則として契約の当事者にはなれません。
たとえば、受益者が財産から収益を得る、受益権を譲渡・変更する権利を持つような家族信託契約を考えると、受益者が生まれていない胎児ではそのような権利行使が不可能です。また、信託の登記や税務上の処理にも影響が出るため、胎児を受益者として記載することは実務上も避けられています。
しかし、将来生まれる可能性のある子どもに資産を承継したいと考える場合、いくつかの対応策があります。たとえば、「信託管理人」を設けて、受益者が将来生まれた場合にその管理人が代行して信託の目的を実行するような設計が可能です。あるいは、出生後に受益者変更を行うことを前提として、最初は別の仮受益者を設定し、子が生まれたタイミングで受益権を移すといった手法もあります。
また、信託契約書の中に「将来出生する子どもが生まれた場合、受益者をその子に変更する旨」を記載しておけば、柔軟に対応できる設計も可能です。このような工夫を行うことで、胎児を直接受益者にできなくても、家族の意向に沿った資産承継を実現することができます。
家族信託では、胎児を直接受益者とすることは法的に認められていませんが、信託管理人の設置や契約書の工夫によって、将来生まれる子どもに資産を承継させる設計は可能です。仮受益者を設定して出生後に受益者変更を行うなど、実務に即した柔軟な対応がカギとなります。意向を実現するには、専門家の助言を受けつつ、将来を見据えた信託設計を行うことが重要です。